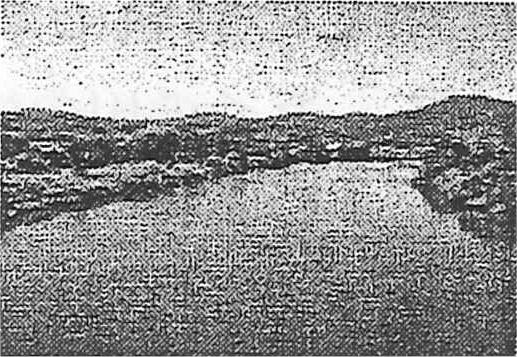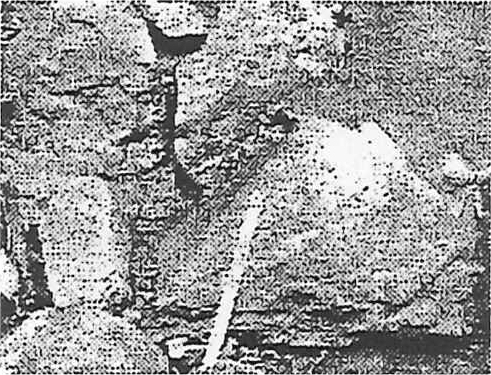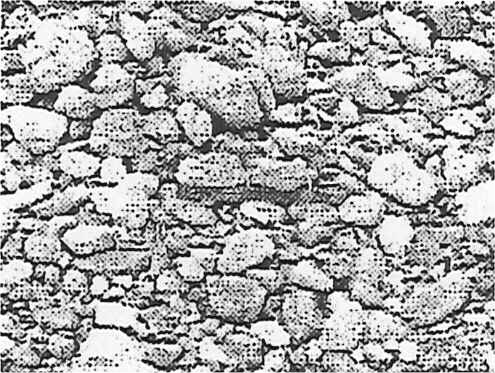| 理科教材ワンポイント講座 |
 |
| 「 流れる水のはたらき 」 |
| 流水実験をベニヤ板で |
| 上流・下流と川原の石 |
| ≪改訂ポイントと指導の工夫のポイント≫ |
| 22年度から扱う新規の内容として、「川の上流・下流と川原の石」が追加されている。
川の様子や川原の原石の形を、流水のはたらきと関連付けながら指導する必要がある。
土を盛って川のモデル実験を行う代わりに、ベニヤ板を用いてモデル実験を行うことで、作業の負担を減らし、繰り返し実験できるなどの利点をいかして指導を行いたい。 |
| 2.単元を構成するにあたって | |||
| ① 子どもたちは・・・ | |||
| ○ | 生活の中で、雨が降った時には水たまりができたり、運動場の端に溝が出来たりしている事を知っている。また、台風など、雨が降った際には川の水が増水し、洪水が起こることを学んでいる。 | ||
| ○ | 4年生の社会科の学習で、武庫川の歴史について学んでおり、その中で堤防を作ったり、洪水の被害についての学習を行っている。 | ||
| ② 何が分かればよいのか。 | |||
| ○ | 流れる水のはたらき | ||
| ・ 地面を削り取る。(浸食作用) | |||
| ・ 削った土を運ぶ。(運搬作用) | |||
| ・ 運んだ土を積もらせる。(堆積作用) | |||
| ・ 水の流れの曲がっているところの水の速さや侵食の差 | |||
| ○ | 川の流れとそのはたらき | ||
| ・ 川の流れは侵食・運搬・堆積作用を通し、長い年月をかけて地形を作っていること。 | |||
| ・ 侵食・運搬・堆積作用は水の量や速さによってその大きさが異なること。 | |||
| ・ 上流・中流・下流の違い | |||
| ・ 川の外側と内側の違い | |||
| ・ 石の形や大きさの変化 | |||
| ・ 災害について(水害) | |||
| ③ 教科書の学びの内容と順序 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3.どのように単元を流すか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【単元導入 流れる水のはたらき 1h】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第1次 地面を流れる水 3h】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第2次 川の流れとそのはたらき 3h】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第2次 川の流れとそのはたらき P.7~11 1h】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●上流と下流の川原の石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第3次 川とわたしたちのくらし 1h】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【補充と発展① 流れる水のはたらき】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||